世界遺産検定の勉強をしていると、
と感じることはありませんか?
世界遺産検定のテキストに登場する建築様式はなんと20個以上!
その中でもよく登場する
- ゴシック様式
- ルネサンス様式
- ロマネスク様式
- バロック様式
を理解しておくと、世界遺産の勉強がしやすくなります。
そこで本記事では、ゴシック様式の概要と、該当する遺産をまとめています。
そもそも建築様式って何?ゴシック様式とは
建築様式とは、ある時代や地域の建築に共通する構造や装飾、設計思想などの傾向のこと。
ゴシック様式は、12世紀後半〜16世紀(諸説あり)のヨーロッパを中心に栄えた建築様式です。
- リブ・ヴォールト
- ステンドグラス
- 高い天井(高い建物)
- 尖塔アーチ
- フライング・バットレス
といった構造が、ゴシック様式の建物に共通しています。

ゴシックは「ゴート人風の」(ドイツ人風の)という意味!
建築技術の向上で造られた「高い天井」が特徴
ゴシック様式の前には、石造りが特徴のロマネスク様式が広まっていました。
石の重さに耐えられるような、厚い壁や小さな窓をもつ背の低い建物が主流で、重量感と威厳のある見た目をしています。
キリスト教への信仰心が高まると、人々は「天国に近づきたい」という思いから、教会などの建物に天井の高さを求めるようになります。
この課題を解決したのが
- リブ・ヴォールト
- フライング・バットレス
まず、天井(ヴォールト)にリブという骨組みを這わせることで、天井がより頑丈な仕組みになりました。
さらに、斜めのつっかえ棒のようなアーチ構造(フライング・バットレス)が、低い建物から高い建物に伸びています。
離れたところにある低い建物の壁や支柱に、高い建物の屋根と壁の重さが分散されています。

重さを分散する2つの仕組みが、石造りの建物に高さを生み出しました!
美的効果も抜群!信仰心に寄り添った鮮やかなデザイン
ゴシック様式は、建築構造のアイデアの秀逸さに目がいきがちですが、その美しさも抜群です。
アーチ構造や薄い壁、大きな窓によって、ロマネスク建築よりも軽やかで明るい印象に!
大きな窓からは天国を象徴する光を多く取り込み、ステンドグラスの窓には聖書などの宗教的な場面が描かれています。

ステンドグラスの色には、実はこんな意味が!
・赤:情熱、エネルギーなど
・黄:知恵、希望など
・青:聖母マリア、安らぎなど
ゴシック様式により、天国を求める人々の心に寄り添った美しい教会が誕生しました。
世界遺産に登録されているゴシック様式の建物
ドイツのゴシック建築
- ケルンの大聖堂
フランスのゴシック建築
- アミアンの大聖堂
- ノートルダム大聖堂 「パリのセーヌ河岸」の構成資産
- サンガティアン大聖堂
- シャルトルの大聖堂
スペインのゴシック建築
- メスキータ 「コルドバの歴史地区」の構成資産
- トレド大聖堂(カテドラル) 「古都トレド」の構成資産
チェコのゴシック建築
- 聖ヴィート大聖堂 「プラハの歴史地区」の構成資産
ポルトガルのゴシック建築
- ポルト大聖堂 「ポルトの歴史地区、ルイス一世橋とセラ・ド・ピラール修道院」の構成資産
※回廊と礼拝堂がゴシック様式で、聖堂はロマネスク様式やバロック様式が混在
ドミニカ共和国のゴシック建築
- サンタ・マリア・ラ・メノール大聖堂 「植民都市サント・ドミンゴ」の構成資産
※ゴシック様式とルネサンス様式の融合
ベラルーシのゴシック建築
- ミール城 「ミール城と関連遺産群」の構成資産
※ルネサンス様式、バロック様式の要素が後から加わった。
ベルギーのゴシック建築
- ノートル・ダム大聖堂 「トゥルネーのノートル・ダム大聖堂」
※創建時はロマネスク様式で、ゴシック様式に改築。
ゴシック様式からルネサンス様式に
ヨーロッパの建築様式は、政治的・経済的な事情や、宗教の発展などに伴って、前の時代に流行った様式を受け継いだり逆らったりしています。
ゴシック様式の次に流行ったルネサンス様式は、バランスの取れた水平的なデザインが特徴で、垂直的な高さを求めたゴシック様式とは対照的です。
ルネサンス様式については、別の記事で書いていく予定なので、合わせて見ていただければ幸いです。

東京大学の「安田講堂」や、長崎県平戸市にある「平戸ザビエル記念教会」の入り口には、ゴシック要素の尖塔アーチが使われています。
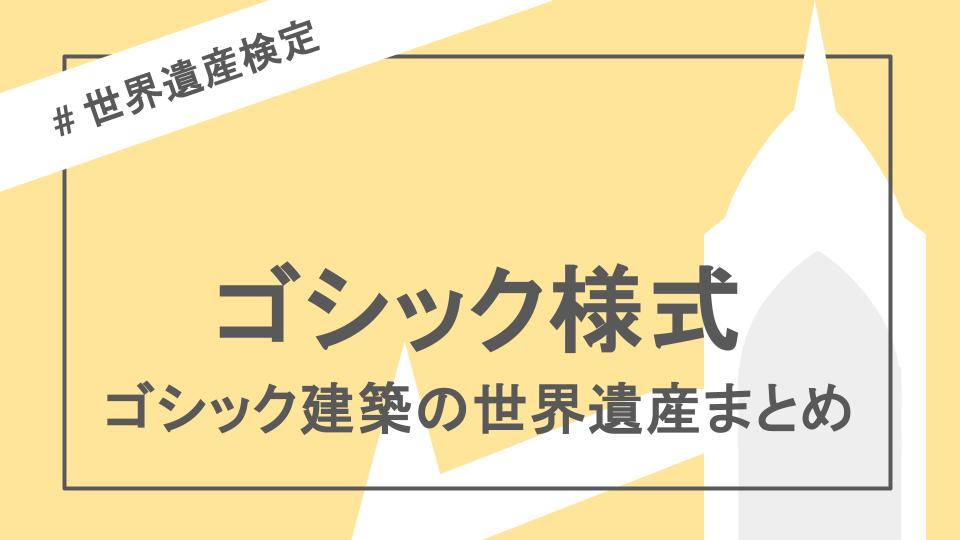
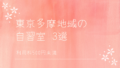
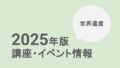
コメント